
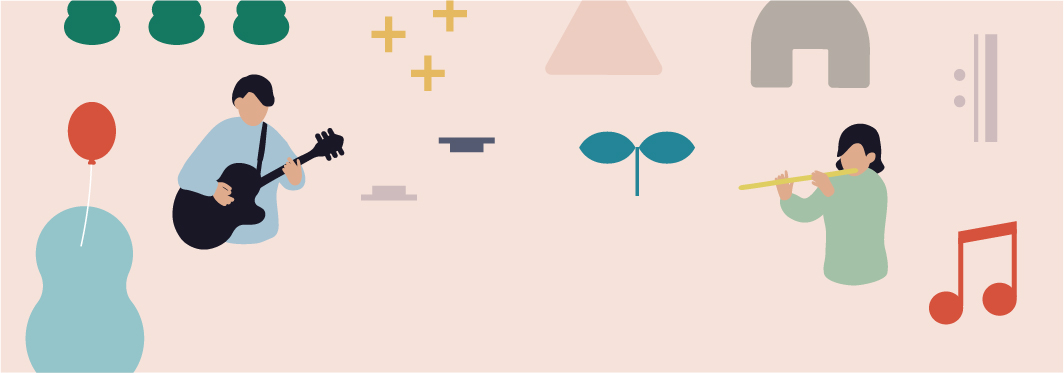

Playback 日比谷音楽祭2023
Report レポート
音楽の魅力の全てを味わい、
振り返り、広げる
『Hibiya Dream Session 3』ライブレポート
実行委員長・亀田誠治が中心となり、日本の音楽シーンで活躍するミュージシャンが集結した日比谷音楽祭恒例のスペシャルバンド・「The Music Park Orchestra」。彼らを中心に豪華ゲストを代わる代わる迎えて行われる夢のセッションが『Hibiya Dream Session』だ。2日目の夜に日比谷公園大音楽堂「YAON」ステージで開催された『Hibiya Dream Session 3』は、「音楽の新しい循環をみんなでつくる、フリーでボーダーレスな音楽祭」のラストにふさわしい光景の連続だった。
亀田が「日比谷音楽祭、最後のセッションです。みんな準備はいいですか!」と呼びかけると、ポップな見た目ながら日本を代表するビートボクサー兼音楽プロデューサーのSO-SOが車の発車音のようなボイスパーカッションで登場!観客からは驚きに満ちた声が漏れ出ている。重厚なビートボックスのリズムとコールアンドレスポンスで会場をダンスフロアにすると、たちまち1曲目の「This Is 8bit」へ突入する。あっという間の数分間は、全て声のみ、ループステーションを使ってリアルタイムで演奏したというから驚きだ。

そしてThe Music Park Orchestraと一緒に演奏したのが「SO-SO Exercise」。SO-SOのビートと観客の手拍子に合わせて亀田誠治 (Ba)、斎藤有太 (Key)、皆川真人 (Key)、山本拓夫 (Sax)と西村浩二 (Tp)、四家卯大 (Vc )と田島朗子 (Vl)、小田原 ODY 友洋 (Cho)、佐橋佳幸 (Gt)、河村"カースケ"智康 (Dr)とバンドメンバーが一人ずつ紹介されながら楽曲に加わっていく。改めて、この日のセッションの豪華さに圧倒される。さて、日中に公園で開催されていたワークショップや音楽マーケットの体験もあってか、日比谷音楽祭の観客は知らない曲でも楽しむ心づもりができているようだ。

続いて登場したのは自身の造語「ブルージーに生きろ」をテーマに活動する、シンガーソングライターのさらさ。J-WAVE「TOKIO HOT 100」で3週連続1位を記録したヒット曲「太陽が昇るまで」を持ち前のスモーキーな歌声で堂々と披露すると、日比谷の“街”の側面が強く押し出される感じがする。続けて、本人の希望でUAの「情熱」をThe Music Park Orchestraと演奏する。1996年の曲が色褪せず、むしろ生き生きと響いてくることに、新時代の歌姫の誕生を予感した。素晴らしい音楽に影響を受けた人がまた新しい音楽を作り、時代を音楽で繋いでいくのだ。

音楽は作り手がいなくなった後も、人々に影響を与え続ける。今年3月にこの世を去った坂本龍一の功績を讃えるように披露したのは、亀田が二十歳の頃に多大な影響を受けたという壮大なインストゥルメンタル「黄土高原」。若干13歳のドラマー・YOYOKAを迎えたThe Music Park Orchestraがスペシャル編成で奏でた。追悼するように空に響かせた時間には、音楽はこの世を超えて届くとまで思えた。
ここまでの出演者からもわかる通り、日比谷音楽祭は若い才能をフックアップすることを惜しまない。YOYOKAは初年度、つまり9歳の時から出演している。SO-SOやさらさも然り、若きアーティストが、キャリアの長いアーティストとの共演の機会を得ることはどれだけ刺激的だろう。これまでそれはテレビの音楽番組などの役割だったかもしれないが、これからはフェスでの共演が、世代を超えた音楽の交流の核となるのかもしれない。

そして日比谷音楽祭が応援するのは、アーティストに限ったことではない。日比谷公園内のASOBIエリア(草地広場)ではESPエンタテインメント東京のギタークラフト科の生徒が、自身が作ったギターについて熱く語ってくれた。また、このレポートを書いている筆者は26歳で、音楽ライターとしてのキャリアは序盤にすぎない。そういった裏方も含めて若手を育てることで業界全体を盛り上げる強い意思が根底にあるから、日比谷音楽祭は未知の体験を生む可能性も大きく秘めている。「音楽の新しい循環」には、音楽に関わる裏方の人が活躍できる土壌作りも不可欠なのだ。
さて、次々と豪華ゲストが登場する『Hibiya Dream Session 3』。続いては日比谷ブロードウェイの井上芳雄と甲斐翔真が登場!アメリカのロックバンドWalk the Moonのヒット曲「Shut Up and Dance」は聴き覚えがある人も多いだろう、一瞬で会場に真夏の空気が訪れる。実はこの曲、現在(6月24日~)、帝国劇場で二人が出演しているマッシュ・アップ・ミュージカル『ムーラン・ルージュ!ザ・ミュージカル』からの選曲だ。20年以上前のミュージカルと現代のポップスが混じり合うのは、まさにボーダーレスな体験といえるだろう。

続いてミュージカル『エリザベート』から「闇が広がる」が披露された。日比谷ブロードウェイに参加予定だった望海風斗が残念ながら欠席ということで、「男性同士のラブソングのように聴こえるかもしれない」と二人がじゃれ合うと、観客からは期待の声が漏れる。劇場も多い日比谷という土地柄がありつつも、野外そして生演奏で披露されるミュージカルナンバーは新鮮だ。
そして、桜井和寿が今回の日比谷音楽祭のために書き下ろした楽曲「雨が止んだら」が披露される時間がやってきた。井上と甲斐が傘を持って演技も交えながら歌っていると、途中から作詞作曲をした桜井和寿本人も合流!「世界のどこかでは 争いが絶えない こんなにも優しい今があるのに」という普遍的で切ない歌詞に、感情がこみ上げた。

楽曲が生まれた背景について「亀田さんとコロナ禍が終わった今、新しい第一歩を踏み出すのにふさわしく、世界で起こっている戦争にもメッセージを送りたい、と話してたんです。その後の帰り道で生まれたのがこの曲です。」と、桜井本人の口で語ってくれた。
「一昨年、このステージで歌いました。その時は無観客で、お客さんの声も聴けなかったんです。その時に“明日こそはたくさんのお客さんの前で歌えますように”という願いを込めて歌ったのがミュージカル『アニー』のテーマ曲『Tomorrow』。それにもう一曲、コロナ禍を果てしない闇に例えて、その奥に手を伸ばそう、というメッセージを込めてMr.Childrenの曲『Tomorrow never knows』を歌いました。そして、今。あの時イメージした明日が、現実として目の前に広がっています。最高に、幸せです。この東京で、大好きな音楽に包まれて、大好きなみなさんの顔を見ながら演奏できる。この喜びを目一杯感じながら、次の曲をお届けしたいと思います。」

桜井が話している後ろで鳴っていたピアノの音が鳴り止み、ギターに弓木英梨乃も参加して披露されたのはMr.Childrenが2008年にリリースした曲「東京」。「この街に大切な場所がある この街に大切な人がいる」という歌詞は、コロナ禍で苦難を強いられたライブハウスから大規模フェスまで、音楽を愛する人が集まる場所について歌っているように聴こえた。無観客での開催だった2021年、そして声出しができなかった2022年の開催を経て今の形があることを、噛み締める。曲が終わるとともに、耳をつんざくほどの歓声が上がった。
続いて披露されたのは、Mr.Childrenがデビューして間もない頃にリリースされた「CROSS ROAD」だった。「コロナが明けた今だから響くのではないか」という亀田のリクエストだという。「真冬のひまわり」という言葉から、日中の『Hibiya Dream Session 2』最後に披露された秦 基博の「ひまわりの約束」を想起する。そう、音楽はひまわりのように凛々しく、勇敢で、周りを明るい気持ちにさせてくれる。コロナ禍に立ち止まり、それぞれがきっと苦しみの中で選択を迫られただろう。音楽業界も例外ではなく、現場を離れることを余儀なくされたスタッフも無数にいた。苦しい時期を乗り越えた人たちによって支えられたこの日のステージは、全ての人の選択を肯定してくれるような勇気をくれた。
「楽しかったですね!みなさん、味わったものをちゃんと振り返って、忘れないようにしてくださいね。噛み締めて、大事に持って帰っていただきたいと思います。今からやる曲がこの日比谷音楽祭最後の曲なので、全曲を振り返りながら行きますよ。思いっきり楽しんでいってください!」
名残惜しさも楽しかった気持ちも全てを投入するような手拍子の中、日比谷音楽祭の最後の1曲を締め括ったのは、1995年から長年たくさんの人を熱狂させ続けているヒットナンバー「シーソーゲーム 〜勇敢な恋の歌〜」だった。音楽は楽しい!難しいことは抜きに、その想いだけで会場を満たしていくようなラストだった。

音楽は悲しい時、そばにいてくれる。苦しい時に乗り越える力をくれる。国も性別も年代も違う誰かと分かち合うきっかけをくれる。そして、それらを超越して、根源的な喜びをくれるのだ。2日間に渡って開催された日比谷音楽祭は、そんな音楽の魅力全てを体感させてくれたフェスティバルだった。桜井の言葉の通り、ここで感じたことは忘れないように繰り返し振り返り、大事にしたい。配信でもう一度あの会場の空気を味わうのもいいし、出会ったアーティストの単独ライブに行くのも良い。CDを買ってもいいし、音楽マーケットやワークショップで出会った楽器の演奏に挑戦してみるのもいい。それぞれが日比谷音楽祭で感じたことを、行動に移すこと。それがきっと、音楽の持つ力が社会を変えていく、その第一歩だ。
文:柴田 真希(しばた まき)









