
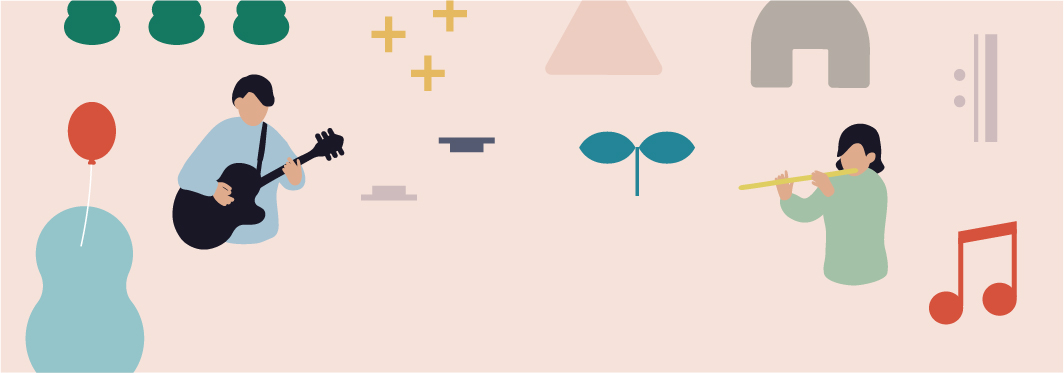

Playback 日比谷音楽祭2023
Report レポート
「新しい音楽の循環」の種を蒔いた、フリーでボーダーレスな音楽祭
日比谷音楽祭2023 初日(6/3)イベントレポート
日比谷公園を中心に開催される日比谷音楽祭は、2019年に始まり今年5年目・4回目の開催となる(2020年は新型コロナの影響により中止)。ライブやワークショップ、トークショーなど、あらゆるコンテンツが無料。そして新進気鋭のアーティストから大御所までが出演するライブは親子孫3世代で楽しめることも評判だ。コンセプトは「音楽の新しい循環をみんなでつくる、 フリーでボーダーレスな音楽祭」。“世代やジャンルや好みを超えてさまざまな音楽に出会える、誰に対しても開かれた場を作りたい”、“ 一人でも多くの人が、音楽が持つ広がりと深さ、そして音楽の楽しみを知るきっかけになりたい”という思いがこめられているのだが、大規模な音楽イベントを参加費無料で運営するためには当然ながらたくさんの資金が必要で、企業からの協賛金や行政の助成金、個人の方からのクラウドファンディングといった支援が欠かせない。支援を集めるのも毎回簡単なことではないが、実行委員長の亀田誠治が「新しい音楽の循環をみんなでつくる、フリーでボーダーレスな音楽祭」の実現を目指すのは、どうしてだろうか。2023年6月3日(土)日比谷音楽祭2023の1日目の様子を振り返りながら、そのテーマについて自分ごととして考えたい。

本来3日間開催だったはずの2023年。初日の6月2日(金)には、フードとお酒と音楽を夜の芝生の公園で楽しむ、日比谷音楽祭初のナイトプログラム『日比谷 YORU 喫茶』の開催が予定されていたが、荒天で中止となってしまい、3日(土)と4日(日)2日間の開催となった。
会場は、今年100周年を迎える日比谷公園大音楽堂(通称:日比谷野音)や小音楽堂、芝生の広場などがある日比谷公園とその中にある日比谷図書文化館、そしてサテライトステージとして東京ミッドタウン日比谷。誰もが自由に出入りできる公園と文化の象徴である図書館を開放し、商業施設まで音楽との接地面を広げる。買い物ついでに遊びに来るのもよし、ワークショップ目的で来るのもよし、ピクニックがてらライブを見るのもよし。自分にあった楽しみ方を探せそうだ。
3日(土)の午前中も、前日からの悪天候の影響でいくつかのステージは残念ながら中止となってしまった。しかし、午後には雨も上がり、お客さんも徐々に集まってくる。この日最初に向かったのは、日比谷公園小音楽堂。到着すると、そこには実行委員長・亀田誠治が開会の挨拶をするためにマイクを持って立っていた。

「昨日、天気も危ぶまれていましたが、いろんな調整をしながら、この時間から開幕することができました。日比谷音楽祭は今年で5年目、節目です。僕がアーティスト一人ひとりに話をして、最高の音楽を届ける契りを交わしています。ライブの他にも、トークショーとかワークショップとか、人生を豊かにするコンテンツがたくさんあります。ここに集まってくださったみなさん、声を聞かせてくれる?(観客の歓声が上がる)今年は声も聞けるということで、嬉しいです。アーティストも本当に全力でパフォーマンスしてくれると思います。だからここからのステージを全力で楽しみにしてください!」

観客の期待値も一層上がった中、福岡出身のバンド「yonawo」が登場。雨あがりの湿度に優しいバンドサウンドの「good job」が観客を癒し、素晴らしい1日の始まりを確信させた。yonawoのライブは若い世代の観客が多いのだが、いつもとはまた違い、幅広い年齢層のお客さんが耳を傾け楽しそうにしている様子を目にすると、日比谷音楽祭のボーダーレスとは、年代に関係なく新しい音楽に触れられるきっかけを生むということだという、一つ答えが見つかった。

公園を出て数分歩くと、東京ミッドタウン日比谷がある。その入り口付近、日比谷ステップ広場「HIROBA」ステージに登場したのは、卓越したギタープレイと等身大の歌詞でファンを増やしている新進気鋭のギタリストでシンガーソングライターでもある「森 大翔(もりやまと)」。1stアルバム『69 Jewel Beetle』が話題となっているので、足を運んだ人も多いだろう。気になっていたアーティストを気軽に見観に行けるのも、フリー=入場無料のいいところだ。

登場するやいなや、アコースティックギターの弦の質感を押し出すような速弾きと複数のリズムが入り乱れるギターソロで一気に聴衆の視線を集める。そのギターの勢いを引き継ぎながら最新アルバムより「台風の目」、続けて「すれ違ってしまった人達へ」を披露すると、その伸びやかでまっすぐな声に惹き込まれた。振り返ると、階段に座ってくつろぐ観客の上には青空が広がり、ガラス張りの東京ミッドタウン日比谷にも空の色が映っている。ギターのリズムをループさせて自身の声を重ね、さらに観客のクラップを重ねる、新世代の演奏スタイルを目の当たりにした。ストレートなラブソング「最初で最後の素敵な恋だから」でもギターのボディを叩き、歌とギターを目まぐるしくプレイする展開に、通りを歩く人が年齢性別問わず立ち止まる。最後の曲「剣とパレット」が始まるとギターに合わせて手拍子が始まり、観客は早くも森のスタイルを飲み込んだようだ。生き生きとしたギタープレイ、そして自分を貫く勇気をくれる楽曲に「自分もギターを弾いてみたい!」と思った人も少なくないだろう。

日比谷音楽祭では、その気持ちのままに、楽器を見て、触って、体験できることも特長だ。にれのき広場の「音楽マーケット」を訪れると、色々な楽器の体験ができるブースが設けられている。インスタコードという目新しい電子楽器やウクレレ、懐かしいアコーディオンや鍵盤ハーモニカ、手軽に触ることができるカリンバ、オカリナまで素材もジャンルも多種多様な楽器がある。ここぞとばかりに、大人も子どもと一緒にはしゃいでいる。

さらにワークショップも充実している。注目の若手ドラマーとして海外での挑戦を続けているYOYOKAによる初心者向けドラムレッスンや、和楽器の体験ワークショップなど、普段身近ではない楽器の魅力をプロに教えてもらえるのは嬉しい。この日筆者が参加したのは「龍声 〜 Ryusei 〜」メンバーによるMusication Village-TAIKEN(日比谷図書文化館小ホール)での和楽器の体験ワークショップ。筆者はお箏を体験したのだが、漢数字の楽譜や絃を弾くため指に爪をつけるのも爪など新鮮で、音を出す楽しさから小学校の音楽の授業を思い出した。他にも琵琶、尺八の体験も大盛況で、子ども連れの家族で参加している人たちや、一人で参加するご年配の人など、世代性別関係なく参加者が一緒に楽器に向かう姿が印象的だった。

気づけばお昼時。フードブースで購入したピザを片手に歩いていると、横長に広がる第二花壇に作られた「KADAN」ステージでは、歌とアコーディオンの姉妹ユニット、「チャラン・ポ・ランタン」が仲間を引き連れて演奏していた。そしてまさかのサプライズ!ステージが終わるとそのまま演奏しながら、日比谷野外大音楽堂まで練り歩いていく。お客さんたちが音楽に手拍子を合わせながら後をつけていく様子はブレーメンの音楽隊さながらで、ステージ上と下の境界も越える、これも「ボーダーレス」な瞬間だった。

続いてKADANステージには日本とアイルランドにルーツを持つトラックメイカーでシンガーでもあるermhoiが、自身のバンド「ermhoi with the Attention Please」で登場した。映画『竜とそばかすの姫』で彼女の声に触れている人は多いに違いない。バンドメンバーには石若駿、マーティ・ホロベック、Taikimenなど国内有数のミュージシャンが揃う。フリーの開催でありながらも、国内トップレベルの演奏を無料で耳に出来るのは、日比谷音楽祭の醍醐味だろう。芝生の後ろには公園を囲う木々、そしてさらに後ろにはビルが立ち並ぶ。都会の中に存在する豊かな緑の中で、風や鳥の声がermhoiの歌声、ハープやさまざまなパーカッションの音の隙間に入り込んで溶けていく。音楽と自然がお互いに相乗効果を生んでいた。

あっという間に夕方になり、「ONGAKUDO」ラストに登場したのはジャズフィールドで活躍する若手ピアニスト壷阪健登とベースボーカル石川紅奈によるユニット「soraya」。「耳を澄ませて」のライブアレンジは、揺れる木々の音、遠くからわずかに聞こえる日比谷の街の喧騒と相性がいい。

ここで会場の魅力にも触れておきたい。日比谷音楽祭で「ONGAKUDO」と呼ばれるステージ、日比谷公園小音楽堂は、ステージ後ろが吹き抜けとなっている。その奥には大噴水、そして日比谷公会堂が見え、客席側は木々で囲まれている。1930年、日本で初めて作られた洋風公園である日比谷公園。その公園の中心にあたり、公園のランドスケープを存分に楽しめるのが日比谷公園小音楽堂だ。その構造を最大限味方につけ、動物たちの鳴き声の中で披露されたのは、アメリカのポップグループ、Carpentersの「SING」。つい口ずさみたくなるメロディに、子どもは母親の膝の上で手を叩き始める。そしてPUFFY「愛のしるし」のジャジーなカバーでそのアレンジ力を見せつけた後は、ベッドタイムストーリーのような自身の楽曲「BAKU」と「ひとり」。ピアノの高音が持つ煌めきは星のようで、夕方の雲ひとつない空に歌声と共に届きそうだった。

小音楽堂を出て噴水広場を散歩していると、そこにはクラウドファンディングのブースが!フリーで開催されている日比谷音楽祭は、協賛金や助成金の他、このクラウドファンディングに大きく支えられている。趣旨に賛同し、楽しかった気持ちを支援金として手渡すことで、今年の開催資金に充てられ、また来年以降の継続開催も応援することができる。
そしてリターンが興味深い。たとえば「会場の子どもたちにオリジナルタオルをプレゼント」コース。6月4日(日)に開催されるDJダイノジのキッズディスコで、子どもたちが使うタオルをプレゼントできるという。そしてなんと支援箱を持っているスタッフに話を聞くと、このブースの運営体験もリターンの一つらしい。本来なら自分がもらうはずのリターンを、誰かのために還元する選択がある。日比谷音楽祭の、こういった点に観客やアーティスト、協賛企業、スタッフ、行政、関わる人みんなでつくり上げる、「新しい音楽の循環」が息づいている。ただ純粋に音楽が好きだ、音楽文化を広げたいという気持ちを中心に、お金や想いが集まってくるのだ。

協賛社ブースにも、その想いが浸透していた。各社が用意したコンテンツは、音楽祭の体験をより豊かなものにするべく考えられたものだ。例えば、写真文化首都・北海道東川町のブースでは、無料で記念写真を撮影してもらえる。テレビ東京『新美の巨人たち』ブースでは、フェイスペイントをしてもらえるということで、終日大人気!こういった体験は「あの日、楽しかったな」と思い出すきっかけにもなるに違いない。

さてブースを楽しんだ後「KADAN」ステージの最後に登場したのは、Shingo Suzuki、mabanua、関口シンゴによるバンド、「Ovall」。メンバーそれぞれがソロミュージシャン、プロデューサーとしても活動する彼らは様々なジャンルの音楽を自身の演奏に取り込み、自然なグルーヴを生み出していく。芝生の上で遊ぶ子どもたちもいれば、夢中で踊る青年もいた。ビールを片手に揺れるカップルもいた。形式にとらわれないOvallの演奏は、聴く人それぞれに違った興奮をもたらすだろう。さまざまな音楽性とそれを楽しむ観客が共生するOvallのステージは、音楽の垣根のなさを一層感じさせた。
多様な音楽に触れる中でこれまでの自分とは違う感覚に出合い、感性や思考を押し広げていくことは、豊かな人生に直結していく。だから偶然訪れた人が不意に耳にするように、公共の場で誰もが音楽を楽しめる場所が必要なのだ。そしてその体験を通して気に入ったCDを買ったり、個別のライブに足を運んだり、クラウドファンディングをすることで、さらに新しい音楽が生まれる根源となっていく。そうやって演者とリスナーの垣根を超えて長く音楽を楽しめる環境を作っていくことは、実行委員長・亀田誠治が大切にしていることだ。日比谷音楽祭で生まれた音楽への愛情の“種”を育て、水をやり、花が咲いたら周りの人に手渡す。そして誰かがまたその種を育てる。そうやってこれからの音楽文化は醸成されていくのだろう。音楽祭の初日は、「新しい音楽の循環」の息吹を感じた一日だった。

文:柴田 真希(しばた まき)









